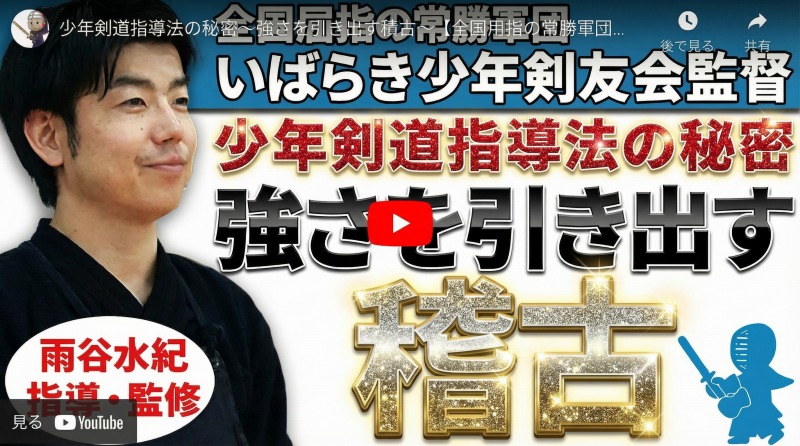
努力はしている。
遅くまで素振りにつきあって、
毎週の道場も欠かさず通って、
ときには泣きながら稽古して。
なのに──
なぜか、勝てない。
勝てそうな場面でも一本が取れず、
他の子がメダルを手にしているのを、
遠くから見つめるだけ。
「うちの子に、何が足りないんだろう?」
「もっと練習?もっと厳しさ?」
……でも、それって本当に正しいのでしょうか?
全国でも屈指の指導実績を持つ
「いばらき少年剣友会」では、
負け続けていた子どもたちが“勝てる子”に変わっています。
しかも、特別な才能があったわけじゃない。
根性論でもない。
時間をかけたスパルタでもありません。
彼らを変えたのは、
いばらき少年剣友会・雨谷水紀七段による、
“たった数ヶ月で結果が出る”と話題の指導法──雨谷メソッド。
この記事では、
その雨谷メソッドをもとに、
✅ 小学生の初心者が試合で勝てない本当の理由
✅ 指導や練習でよくある“落とし穴”
✅ 親や先生ができる、勝てる子への“関わり方”
をお話しします。
もし、今のお子さんや生徒に「もっと伸びてほしい」と思っているなら──
この方法を知っているかどうかが、大きな分かれ道になるかもしれません。
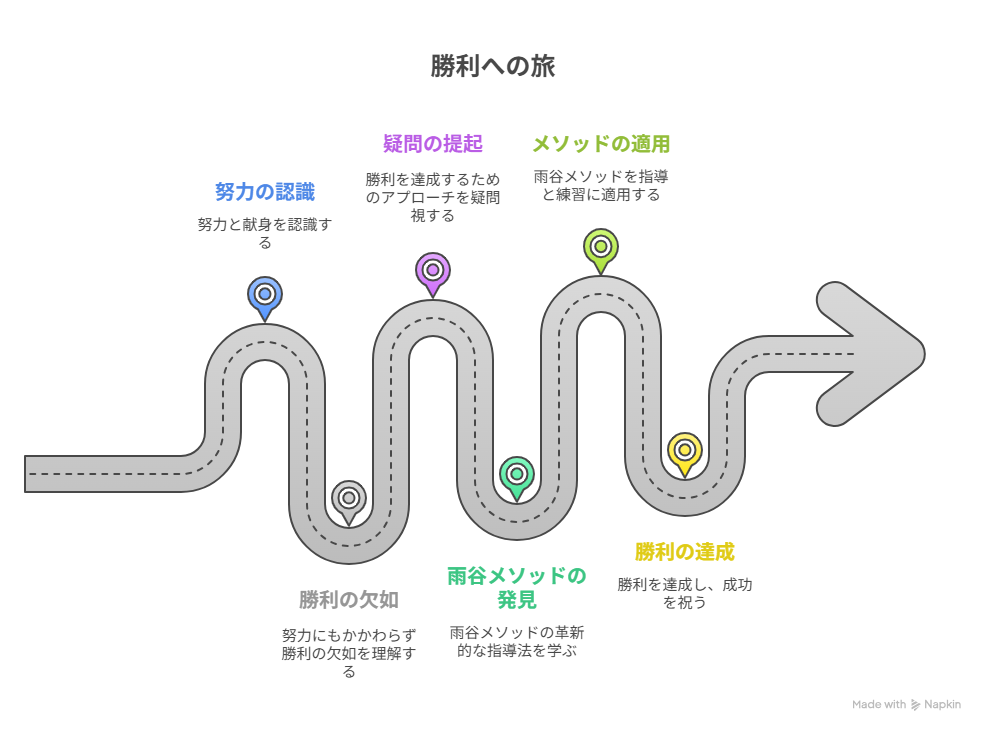
小学生剣道の初心者が抱える3つの課題
「どうして、あの子だけ勝てないんだろう」
道場の隅で、つぶやくように言った親御さんの声。
思い当たる方、多いのではないでしょうか。
毎日素振りをやって、
道場にも早く来て、
とにかく真面目に頑張ってる。
なのに──
なぜか、試合になると勝てない。
1回戦で負けて、
帰りの車内は沈黙。
「なんで?」という気持ちと、「言えない」空気だけが残る。
でも、安心してください。
勝てないのは、才能や根性の問題じゃありません。
ほとんどの子がつまずいている「3つの壁」。
そこを正しく理解することで、
初心者でも“勝てる子”に変わる道が見えてきます。
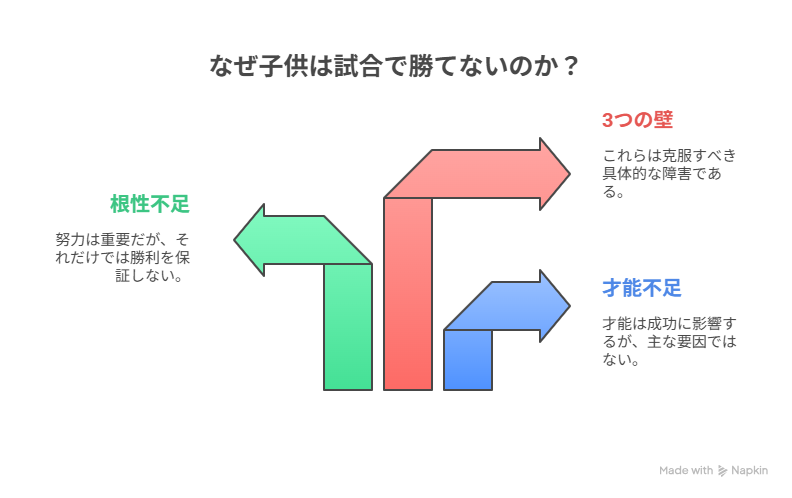
課題1:試合で緊張して動けない
普段の稽古ではちゃんと動けるのに、
試合になるとカチコチに固まってしまう。
これ、実は“あるある”です。
原因はひとつ。
「頭で考えすぎて、体が動かなくなっている」んです。
剣道は反射と直感が命。
「迷い」が出た瞬間、負ける。
いばらき少年剣友会では、
実戦形式の稽古が日常的に組まれていて、
身体が自然と反応するようになる稽古メニューを用意しています。
課題2:基本はできても実戦で通用しない
これも多いです。
“基本通りにやっている”のに、一本が取れない。
それは、
「技をつなげる導線」が抜け落ちているから。
いばらき少年剣友会では、
基本と応用を“連動”させる仕組みが稽古に組み込まれています。
たとえば、
跳躍素振り → すり足 → 出小手というように、
流れのある練習を取り入れることで、
実戦で使える「つながる技」を身につけていく。
これが「基本だけじゃ勝てない問題」の突破口になります。

「うちの子だけ勝てない……」そんな悩みを抱えていませんか?
実は、その“つまずき”、あなた一人じゃありません。
👉子どもが負け続ける理由と、
そこから抜け出す方法がわかります。
↓↓↓
少年剣道指導法の秘密~強さを引き出す稽古~【全国屈指の常勝軍団 いばらき少年剣友会監督雨谷水紀 指導・監修】
課題3:親や指導者の言葉がプレッシャーに
「ちゃんとやれば勝てるのに」
「もっと気合いを入れて」
その言葉、
本当に“届いて”ますか?
子どもにとって、それは応援じゃなく、
「責められてるように聞こえる」ことも多いんです。
雨谷先生は、ここに敏感です。
「もっと出せ」ではなく、
「声を出すと、自分も楽になるよ」という伝え方。
“気づき”を促す言葉が、子どもを変える。
いばらき少年剣友会の道場は、
ミスしても責められない。
だから子どもたちは、安心して挑戦できるんです。
いばらき少年剣友会が大切にする指導の基本
「最近、うちの子……剣道を楽しめてないかも」
そう感じたこと、ありませんか?
はじめは嬉しそうだった。
防具を着るたびに、ちょっと誇らしげだった。
それが今では、
試合前になると「お腹が痛い」と言い出す。
朝、稽古の日はやたらと機嫌が悪い。
「好き」だった剣道が、「しんどいもの」になっている。
これ、珍しい話ではありません。
むしろ──
多くの子が、静かに“剣道嫌い”になっていく現実があります。
でも、
それを変える「指導のあり方」が、いばらき少年剣友会にはあります。
子どもが主体的に動く“声かけ”の工夫
「早く打て!」
「構えが甘い!」
よくある指導の言葉。
悪気はなくても、
“命令口調”は、子どもの心を閉ざしやすい。
雨谷先生は、そうした“指示”を、
“問いかけ”に変えることを大切にしています。
たとえば──
「今の場面、次はどうしたいと思う?」
「今の動き、自分ではどう感じた?」
この一言だけで、
子どもの表情が変わる瞬間があります。
責められるのではなく、考える機会になる。
だから、自分から動こうとする。
「言われて動く子」から、「気づいて動く子」へ。
この変化が、強さにつながっていきます。
「短時間×高集中」の質重視の稽古法
剣道で強くなるには──
「長時間やらなきゃ」と思っていませんか?
でも、ちょっと待ってください。
疲れきって、惰性で振る竹刀に、意味はあるのでしょうか?
雨谷メソッドでは、
1時間でも濃い内容の稽古を追求します。
「たった10分、この動作だけ集中」
「3本だけ、本気で勝負しよう」
それだけ?と思うかもしれませんが、
集中と意図のある反復は、子どもを“自信満ちた剣士”に変えます。
終わったあとに、
「今日は、なんか掴めたかも」
そう感じられる練習が、自己効力感を育てるんです。
だから、長くなくていい。
短くても、密度のある稽古。
これが、伸びる子の“共通点”です。
失敗から学ばせる“安心できる道場”の空気
そして、もう一つ。
とても大切なのに、見落とされがちなこと。
それが──
「失敗にどう向き合えるか」という道場の空気です。
泣きながら戻ってきた子。
自分の負けを悔しがる子。
そのときに、
「だから言っただろ」
「なんでできないんだ」
ではなく──
「悔しかったな。次はどうしたい?」
という“声かけ”がある道場。
子どもが挑戦することを恐れなくなる場所。
それが、いばらき少年剣友会です。
この空気の違いが、
「剣道=楽しい」「剣道=またやりたい」という気持ちを生み出します。
結果、子どもたちは自然と伸びていく。
勝ちにいく前に、まず「続けたい」と思える環境を。
これが、いばらき少年剣友会の“最強の土台”です。
👉いばらき少年剣友会の練習方法を見てみる
↓↓↓
少年剣道指導法の秘密~強さを引き出す稽古~【全国屈指の常勝軍団 いばらき少年剣友会監督雨谷水紀 指導・監修】
初心者が試合で勝つための上達ポイント
「うちの子、なんで勝てないんだろう。」
剣道を始めて1年、2年。
地道に稽古を積んできたのに、なぜか試合では結果が出ない。
……それ、“努力が報われていない”のではなく、報われる方法を知らないだけかもしれません。
雨谷メソッドでは、
「初心者でもすぐに成果が出やすいポイント」を明確に押さえています。
ここでは、いばらき少年剣友会の指導でも重要視されている、
“勝てる子”に変わるための具体的な3つの上達ポイントをご紹介します。
勝てる足さばき:「左足引きつけ」とリズム
まず、ここを軽視していると伸びません。
足がバラバラのまま、技術を乗せようとしても、実戦では通用しない。
雨谷先生は、「左足の引きつけ」とその“速さ”に注目しています。
たとえば──
・リズムジャンプから入る足さばき
・「止まらないすり足」の感覚を染み込ませる反復
・竹刀を振らず、足だけで打突のリズムを作る練習
こうした地味な動作の積み重ねが、
試合で「間を支配する」力になります。
そして、気づけば──
一本が“勝手に出る”ようになっていく。
一本に繋がる打突:「間」の感覚の習得
剣道では技そのもの以上に、
“いつ打つか”のタイミングが命です。
その正体が「間」。
でも、この「間」を教えられる指導者は、実はそう多くない。
いばらき少年剣友会では、
間合いを「感覚」ではなく「技術」として教える工夫があります。
・タイヤ打ちを使った「ため」の感覚づくり
・高低差のあるすり足で“ズレ”の中での打突を覚える
・「出小手」の間合いを1cm単位で調整する稽古
これ、まるでトップアスリートの感覚トレーニング。
でも、それを小学生でもできる形に分解して伝えているのが、雨谷メソッドのすごいところ。
「なんか当たった」ではなく、
「ここで出れば決まる」とわかって動ける。
この違いが、勝敗を大きく分けます。
自信を育てる:試合前のルーティンと声かけ
そして最後に、
技術よりも大事な“心の整え方”。
練習では完璧なのに、試合で崩れる子がいます。
これは、メンタルの準備ができていないだけ。
雨谷先生は、こう言います。
「プレッシャーは消せない。でも“慣れさせる”ことはできる」
いばらき少年剣友会の子どもたちは、
試合と同じ空気感を稽古中に何度も体験します。
加えて、保護者にも「試合前の声かけ」のアドバイスが。
「大丈夫?」ではなく、
「楽しんでおいで」
「勝つのが目的じゃない、出し切るのが目標だよ」
このひと言が、子どもを軽くする。
結果として、動きが自然になり、一本が出る。
心と体はセットです。
それを、稽古の中で整えていくのが、いばらき少年剣友会の指導の真髄です。
地道な練習が、“勝てる動き”に変わる瞬間。
あなたのお子さんにも、必ずその日が来ます。
👉雨谷メソッドで、試合で結果を出す
“体の使い方”が手に入ります。
↓↓↓
少年剣道指導法の秘密~強さを引き出す稽古~【全国屈指の常勝軍団 いばらき少年剣友会監督雨谷水紀 指導・監修】
保護者・指導者ができるサポートの工夫
「もっと声出しなさい!」
「どうしてそんな簡単なことができないの?」
……つい、言ってしまいますよね。
本気だからこそ、勝たせたいからこそ。
でも──
その“正しさ”が、子どもを動けなくしているかもしれません。
指導法も大事。
練習量も大事。
でももうひとつ、見落とされがちな視点があります。
それが、
「関わり方の質」です。
「なぜできないの?」より「どこが難しい?」
あるあるなのがこのセリフ。
「もう何度も言ってるよね?」
「昨日もやったじゃん?」
それ、本当に伝わってますか?
子どもは、「できない」のではなく「わからないままやっている」ことがほとんどです。
ここで差がつくのが“問い方”。
「なぜできないの?」と問えば、
子どもは“責められている”と感じる。
でも、
「どこが難しかった?」と聞くと──
子どもは“話していいんだ”と感じます。
同じ問いでも、与える印象がまるで違う。
剣道が上達する前に、
“話せる環境”が整っていること。
これが、実は技術よりも先に必要だったりします。
失敗を肯定する関わりが子どもを強くする
一本取られたとき、
稽古で叱られたあと、
泣きながら帰ってきた日──
そのときに何を言うかが、
子どもの“心の強さ”を決める瞬間です。
「だから言ったじゃない」
「何度やったらできるの」
言いたくなる。でも、ちょっと待ってください。
いばらき少年剣友会の保護者さんたちは、
その瞬間に“声をかけない”ことも選びます。
無言で抱きしめる。
話してくれるまで待つ。
落ち着いてから、
「悔しかったね。ちゃんと見てたよ」と伝える。
その結果、
子どもたちは“失敗しても、見放されない”と知る。
それが、次の挑戦へと向かうエネルギーになるんです。
一緒に成長するという意識を持つ
剣道をするのは子どもですが、
支える親や指導者の“姿勢”も、一緒に成長しています。
たとえば──
・子どもと一緒に目標を立てる
・練習後、「今日よかったところ」を本人に言わせる
・勝っても負けても、まず「お疲れさま」と伝える
小さなことかもしれませんが、
その積み重ねが、親子や師弟の“信頼関係”になっていく。
勝ちを目指す過程で、
時にイライラしたり、焦ったり、落ち込んだりもします。
でもそのたびに、
「この子と一緒に進んでるんだ」と感じられる関わりができたら、
結果はあとから、自然とついてきます。
いばらき少年剣友会 まとめ
ここまで読んでくださった時点で、
あなたはもう、勝てない原因を“才能や努力不足”のせいにしていないはずです。
それは、
本当に子どもの可能性を信じている証拠。
いばらき少年剣友会・雨谷水紀先生の指導法は、
「子どもを勝たせる」のではなく、
「子どもが自分で勝ちに行ける力を育てる」もの。
その視点を持てる大人が、
いま、全国の道場や家庭に求められています。
もう、闇雲に厳しくする時代ではありません。
長時間稽古しても、結果が出ないとしたら、
やり方そのものを、見直すタイミングかもしれません。
雨谷メソッドが教えてくれるのは、
✔ 実戦で使える動きの習得法
✔ 試合で一本を取るための“間”の感覚
✔ 子どもの自信を引き出す関わり方
そして何より、
子どもが「剣道って楽しい!」と感じ続けられる指導です。
あなたのお子さんや教え子が、
今、結果に苦しんでいたとしても──
その姿を、
“変われる可能性がある子”として見てあげてください。
勝てる子は、生まれつきじゃない。
勝てる子は、“関わり方”で育つ。
それを証明してくれるのが、
いばらき少年剣友会の子どもたちであり、
雨谷先生の30年にわたる実績です。
さあ、今日から。
まずは一つ、声かけを変えてみるだけでもいい。
子どもは、大人が思っている以上に、ちゃんと変わってくれます。
ただ、「変われる場所」と「見守ってくれる存在」が必要なだけ。
その一歩として、この記事が少しでも力になれたら嬉しいです。
勝てない日々は、今日で終わらせましょう。
子どもの目に、自信と笑顔を取り戻す第一歩を。
👉たった3ヶ月で、子どもが“変わった”という声が
全国から届いています。
↓↓↓
少年剣道指導法の秘密~強さを引き出す稽古~【全国屈指の常勝軍団 いばらき少年剣友会監督雨谷水紀 指導・監修】
